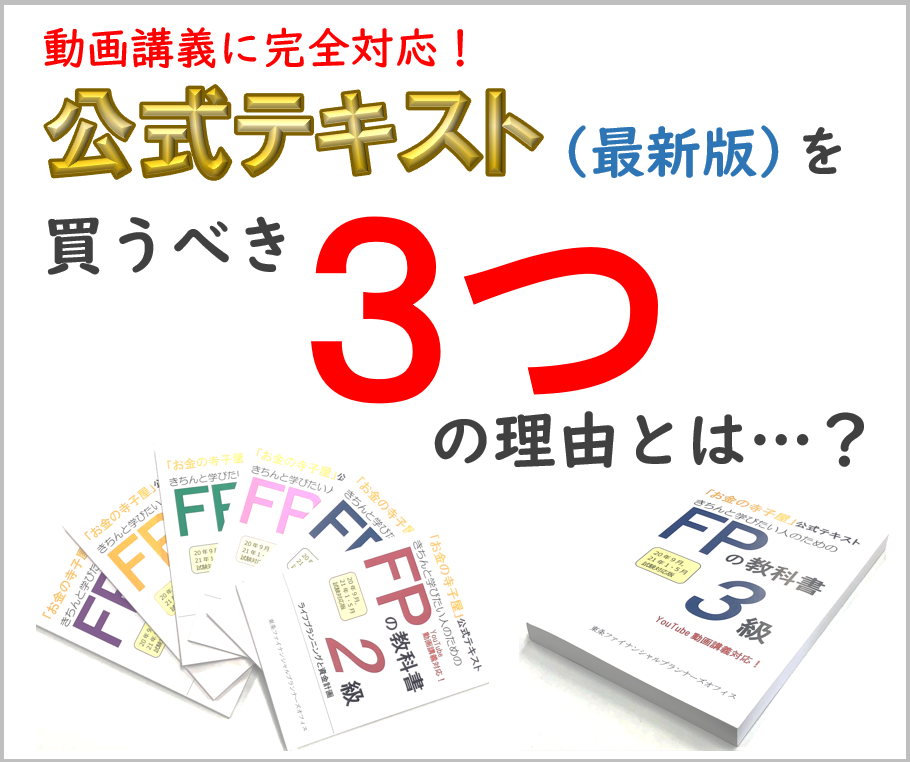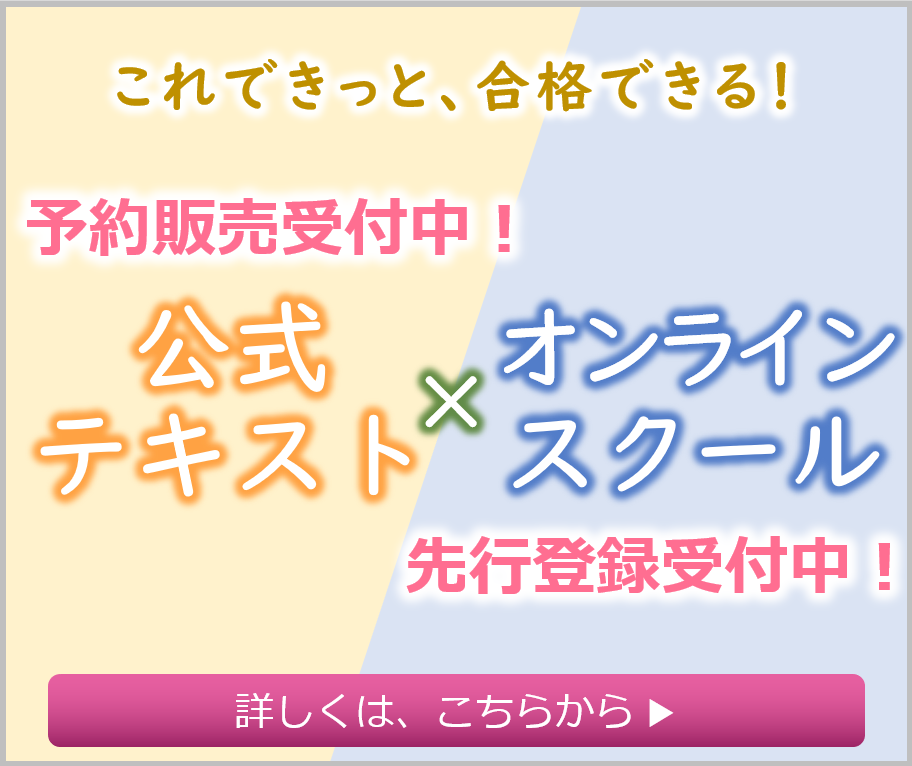3級正誤問題(2018年9月)-不動産
【問22】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約に適合しない箇所がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
【答22】
×:買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その事実を知った時から1年以内に売主に通知しなくてはいけません。
【問23】
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
【答23】
×:普通借家契約の説明です。定期借家契約は、再契約はできますが、更新はできません。
【問24】
不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
【答24】
×:不動産取得税は、相続による取得では課税されませんが、贈与による取得では課税されます。
【問25】
譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。
【答25】
○:譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分されます。
  |
【問51】
宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
| 1. | 一般媒介契約 |
| 2. | 専任媒介契約 |
| 3. | 専属専任媒介契約 |
【答51】
正解:1
「専任」がつく媒介契約は、重複依頼ができません。
「専任」がつく媒介契約は、重複依頼ができません。
【問52】
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
| 1. | 防火地域 |
| 2. | 準防火地域 |
| 3. | 敷地の過半が属する地域 |
【答52】
正解:1
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全体に、規制が厳しい方(防火地域)の規制が適用されます。
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全体に、規制が厳しい方(防火地域)の規制が適用されます。
【問53】
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
| 1. | 3分の2 |
| 2. | 4分の3 |
| 3. | 5分の4 |
【答53】
正解:3
建て替え決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数により可決します。
建て替え決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数により可決します。
【問54】
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
| 1. | 2年 |
| 2. | 3年 |
| 3. | 5年 |
【答54】
正解:2
固定資産税評価額は、原則として3年おきに評価替えされます。
固定資産税評価額は、原則として3年おきに評価替えされます。
【問55】
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、 損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で( )以内である。
| 1. | 3年 |
| 2. | 5年 |
| 3. | 10年 |
【答55】
正解:1
居住用不動産を売却して譲渡損失が生じた場合、一定要件を満たせば損益通算の対象となり、通算しきれなかった金額については、最長3年間繰越控除する事が出来ます。
居住用不動産を売却して譲渡損失が生じた場合、一定要件を満たせば損益通算の対象となり、通算しきれなかった金額については、最長3年間繰越控除する事が出来ます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | 一覧へ | 進む> |
| <前回同分野 | 次回同分野> |